
写真はイメージです。
書き初め(かきぞめ)は、新年に特有の伝統的な習慣で、一年の抱負や目指す目標を表現するために行われます。書き初めは、いつ書くのか。意味や由来や、どのような言葉や四字熟語が適しているのかについて、調べましたので徹底解説いたします。
書き初めは、いつ行う?
書き初めとは、新年の始まりを祝って行う日本の伝統的な習慣です。現代では、1月2日に書き初めを行うことが一般的です。この日は、書道や茶道、三味線などの芸道を始めるのに最適な日とされており、多くの習い事がこの日を初稽古としています。
歴史を振り返ると、平安時代には「吉書の奏」として縁起の良い日に書き初めが行われていましたが、室町時代には「吉書始め」として1月2日に大規模に行われるようになりました。これは、1月2日という日付が書き初めに特別な意味を持つようになった理由の一つです。
また、新年に初めて汲む「若水」を神前に供えた後、食事など様々な用途に使用されていました。元旦の忙しい行事を終えた後、2日に書き初めを行うことは、当時の生活習慣としても自然な流れだったと言えます。
このように、書き初めは、新年を迎えた日本の文化において、歴史的にも現代的にも重要な位置を占めています。
書き初めの意味は?
1月2日に行われる書き初めには、どのような特別な意義があるのでしょうか。書き初めの意味は、以下の2つの意味があります。
書の向上を願う
新年の始まりに、神聖な若水を使用して書を行うことは、神の恩恵を借りて文字の技術を向上させる願いを込めた行為です。
一年の目標を新たに定める
吉祥の言葉や詩、あるいはその年の目標や意気込みを記すことで、一年の行動を心機一転させる意味合いが含まれています。
書き初めの由来は?
書き初めの起源は、平安時代の宮廷で行われていた「吉書の奏」という儀式にさかのぼります。
この儀式は、改元、新しい皇族の誕生、年の始まりなど、重要な時期に天皇へ文書を捧げる行為でした。本質的には行政的な手続きであったものの、その内容は主に儀礼的で、国の平和や安定を祝福する言葉が記されていました。
この伝統は、鎌倉時代や室町時代を通じて幕府にも継承され、「吉書始め」として新年の式典として定着しました。その際に作成される文書は、吉書奉行によって丁寧に毛筆で清書されていたとされます。
江戸時代には、「吉書始め」という行事が一般の人々にも浸透し、「新年を祝う書道行事」として広く行われるようになりました。その典型的な例として、1804年頃に歌川豊国によって描かれた、寺子屋での書き初めのシーンを捉えた浮世絵があります。
この時代、幕府の要職に就くための試験には「書」と「そろばん(計算)」の2つの科目がある「筆算吟味」というシステムが存在し、良い筆跡は重要な教養の一つとされていました。
また、江戸時代の家庭での書き初めの習慣としては、新年に最初に汲んだ井戸水(若水)を神前に供えた後、その水で墨を磨り、恵方を向いて詩歌を書くことが一般的でした。
書き初めで、おすすめ言葉や4文字熟語は?
書き初めに用いる言葉は、新年に相応しいものであれば何でも良いですが、ここではいくつかの推奨される言葉を紹介します。
飛翔(ひしょう)
二文字で構成される書き初めでは、この言葉がよく使われます。新年に相応しい吉祥な意味を持ち、はねや点などの筆使いが含まれているため、書くのが意外にもバランスをとるのが難しいかもしれません!
挑戦(ちょうせん)
新年の目標として最適な言葉の一つです。「挑」「戦」という文字は、そりやはらいの技法を多く使うため、気持ちを込めて勢いよく書くのが良いでしょう。
時哉(ときかな)
「今こそその時!」という意味合いの言葉で、現在が重要なタイミングであることを自覚し、この瞬間に精進すべきだという自己戒めの意を含んでいます。
荷心香(かしんかんばし)
三文字で構成される書き初めはバランス取りが難しいですが、その意外性が面白いものです。通常の半紙に一行で書く方法も一つの選択肢です。「荷心」という言葉は、ハスの花を指し、泥沼から美しい花を咲かせ、香りを放つことから、「どんな困難な状況でも自分の本質を失わない」という意味が込められています。
守破離(しゅはり)
この言葉は、茶道や武道などを学ぶ際の心構えや進行段階を示しています。最初には指導された教えを忠実に守り、次には教えられた型を超えて新たな挑戦をし、最終的には学んだすべてを超えて自由自在な段階に到達することを意味しています。書道においても、このような進化を目指すことが望ましいでしょう。
一期一会(いちごいちえ)
この言葉は禅の教義に由来しており、同一の瞬間は決して再びは訪れず、毎日が一生に一度だけの特別な出会いであることを示しています。漢字は難しすぎない難易度で、とめ、はね、はらいがバランスよく配されており、書き初めに適した定番の選択肢となっています。
心機一転(しんきいってん)
何かの出来事を契機にして、心がポジティブな方向へと変わることを表す言葉です。特に新年にふさわしい表現でしょう。「心」という字が含まれる言葉は、書き初めや揮毫(書を力強く美しく書くこと)で頻繁に用いられる傾向があります。
一意専心(いちいせんしん)
一つのことに集中し、気を散らさずに粘り強く続けることを意味します。長期間続けている大切なことがある人にとって、新年に意志を固めるために選ぶのに適した言葉です。
直感精読(ちょっかんせいどく)
直感やひらめきが物事の核心を捉えることが多いため、それを大筋の計画に据え、細かい部分を詰めていくという意味の言葉です。特に勝負をする際の心構えとして語られることが多く、棋士なども好んで用いる言葉だと言われています。
転凡成聖(てんぼんじょうしょう)
禅の教えに基づくこの言葉は、平凡なものでも素晴らしさを持ち得る、日常生活の中にも悟りが存在するという意味を持っています。言葉の意味は深いですが、漢字自体は複雑ではないため、書くのに向いている言葉と言えます。
まとめ
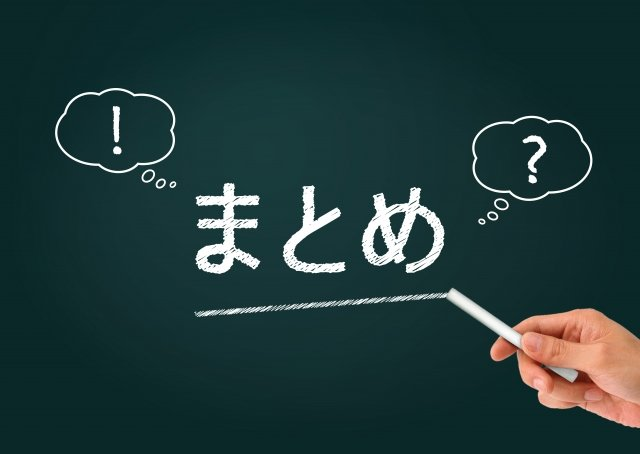
書き初めは、いつ書くのか。意味や由来や、どのような言葉や四字熟語が適しているのかについて、解説いたしました。
1.書き初めは、いつ書くのか?
(1) 1月2日に書き初めを行うことが一般的。
2.書き初めの意味は?
(1) 書の向上を願う
(2) 一年の目標を新たに定める
3.書き初めの由来は?
(1) 書き初めの起源は、平安時代の宮廷で行われていた「吉書の奏」という儀式である。
4.書き初めで、おすすめ言葉や4文字熟語は?
(1) 飛翔(ひしょう)
(2) 挑戦(ちょうせん)
(3) 時哉(ときかな)
(4) 荷心香(かしんかんばし)
(5) 守破離(しゅはり)
(6) 一期一会(いちごいちえ)
(7) 心機一転(しんきいってん)
(8) 一意専心(いちいせんしん)
(9) 直感精読(ちょっかんせいどく)


コメント